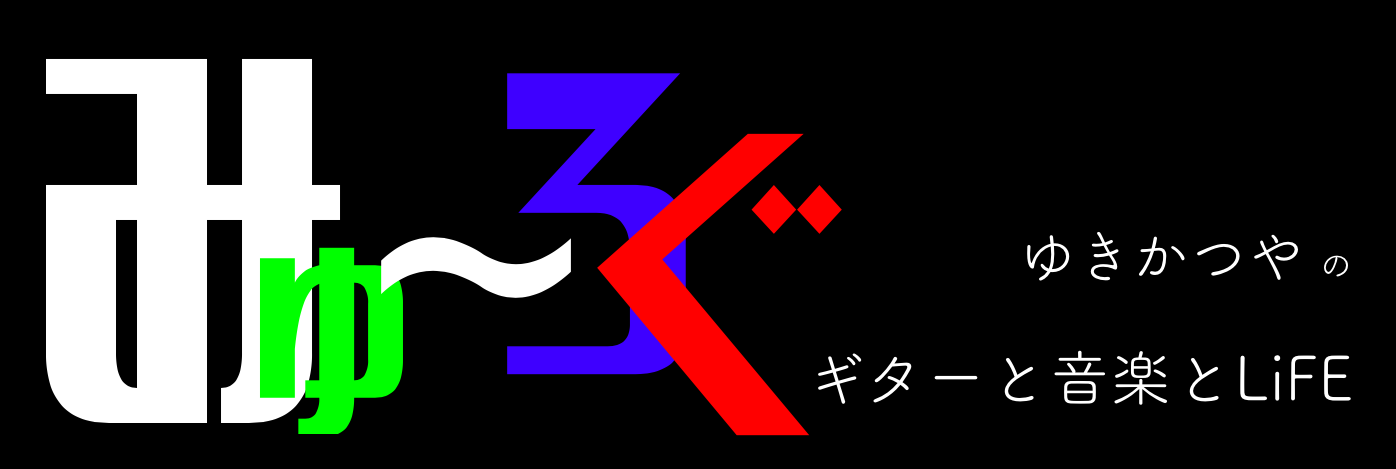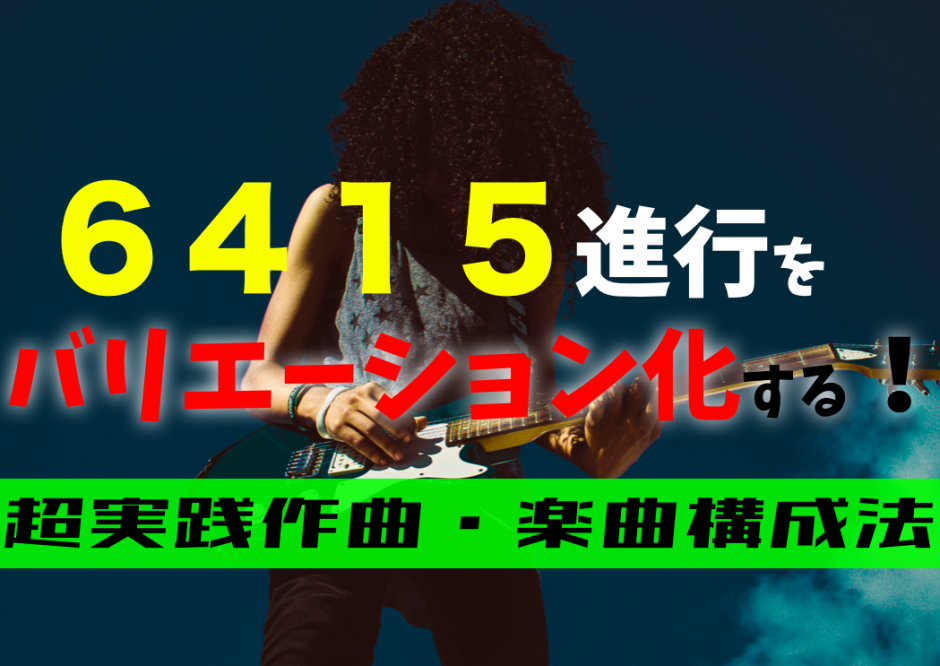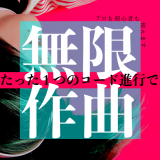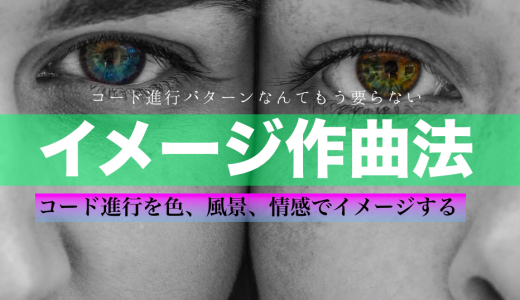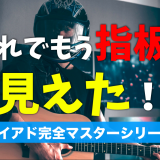ギタリストのゆき かつや(@manic_lab)です。
ギター歴32年目。プロデビュー19年目。音楽を全力で愛して生きてます。レッスンでは現在約60名の生徒さんを指導中→詳しくはプロフへ
作曲をするとき
6415進行、使いすぎてもう”ネタ切れ”してませんか?
当サイトの人気記事、【プロも使う】たった1つのコード進行で無限に作曲!【初心者OK】で6415進行というコード進行を紹介しました。
この6415進行。
海外ではポップパンク進行とも呼ばれ、まあとにかくいろんな曲で使われまくってます(10年代のEDMはもうこればっかり)。
邦楽でも、洋楽志向のアーティストがよく使ってますが、やはり日本的な情緒を表現するためには6415のループだけでは味気ないんですよね。
今回は、6415進行をさらに表現豊かにするバリエーションのアイデアを紹介します。
※この記事は3分ほどで読み終わります
もくじ
6415進行のバリエーションを増やす超実践アイデア【作曲・音楽理論】
6415進行とは?
6415進行とは、ダイアトニックコードの
Ⅵ(6)ーⅣ(4)ーⅠ(1)ーⅤ(5)
と進行するコード進行です。
主に楽曲のサビなどで繰り返して使われることで、メロディを強烈に印象付ける非常に使えるコード進行ですね。
マイナートニックから始まるのに暗い感じにはならずに
・力強さ
・確固たる意志、決意
・グイグイ攻める感じ
・とはいえ、切なさ
・壮大さ、ドラマティック
を表現するには最高にピッタリのコード進行です。
ダイアトニックコードに関しては、【音楽理論】ダイアトニックコードという神の無双ツールを使う!で詳しく解説しています。
 【音楽理論】ダイアトニックコードという神の無双ツールを使う!
【音楽理論】ダイアトニックコードという神の無双ツールを使う!
6415進行の実際の使われ方
キーCで6415進行を書くと
|Am |F |C |G |
となります。
サビなどでこの6415進行を繰り返し使うわけですが、テンポとビートによって定番の使い方があります。
16ビートでの6415進行の使い方(使用頻度 ★★★★★)
16ビートでBPM72〜90では
|Am F |C G :||
というように、2拍ずつのコードチェンジになります。
実際にギターやピアノで演奏してみたら分かりますが、1小節ずつのコードチェンジだと間延びしてしまうからです。
実際にこのテンポ感で16ビートで6415進行を使うロックな曲は星の数ほどあります。
8ビート、4つ打ちでの6415進行の使い方(使用頻度 ★★★★)
8ビートでBPM108〜200(over)では
|Am |F |C |G :||
というように、1小節ずつ4小節ループで使います。
テンポが速い8ビートだと2拍ずつだと、早すぎてメロディがうまく乗りません(例外はあります)。
EDMなんかはまさにこのパターンです。
楽曲での6415進行バリエーションの作り方【構成・楽曲展開】
では、実際の楽曲で6415進行のバリエーションをどう作っていくのか解説します。
コードをテンション化する【6415進行バリエーション】
まずはコード進行はそのままに、それぞれのコードをテンションコードにする技です。
|Am |F |C |G :||
↓
|Am9 |F9 |C6 |G13 :||
FはFM7でもイイのですが、あえてF9にすることでグッとくる引っ掛かりができます。
ギターでヴォイシングするならこんな感じ。
テンションのバリエーションは他にも考えられるので色々研究してみてください。
リズムはボサノバにしてお洒落カフェラウンジ的にもできるし、16ビートシャッフルでネオソウル的にもできますね。
繰り返しを変化させる①【6415進行バリエーション】
次は楽曲のサビの構成を考えたバリエーションです。
実際の楽曲作りの流れを追いながら見ていきましょう。
BPM83の16ビートで、サビをこの4小節で始めるぜ!と曲作りをしているとします。
|Am F |C G |
では、次の2小節も同じ繰り返しにすると。。。
|Am F |C G |
|Am F |C G |
まあ、あえて打ち込みで洋楽っぽいループな感じを狙って、ならこれでも良いのですが。
J-POPやJ-ROCK的に考えるとちょっと変化が欲しいですね。
じゃあ、こうしますか?
バリエーション①
|Am F |C G |
|D |Esus4 E |
おお〜、これはこれでイイ感じですが。。。
サビの最初に持ってくるにはちょっと展開が大きすぎてもったいないかも、ですね。これはサビの締めに持ってくるのが良いんじゃないでしょうか。
サビの入りとしては、6415進行の繰り返しのループ感でメロディを印象付けたいわけです。
なので、こうします。
バリエーション②
|Am F |C G |
|Am F |Dm7 E7 |
2回目も6ー4の部分は残して繰り返し感を出しつつ、残り1小節で少し変化させる技です。
日本的なメロディアスな叙情感も入ってきますよね。
一番最後がE7で、またAmに繋げるのであればこういうコード進行もありです。
バリエーション③
|Am F |C G |
|Am F |Bm7 E7 |
これもマイナードミナントが入ってきて日本人の好きな感じになってます。
少し変わった感じにしたい場合は、こういうのもありです。
バリエーション④
|Am F |C G |
|Am F |Ab G |
メロディをちょっと工夫しないといけないですが、コード進行から新しいメロディが呼ばれる感じがして面白いですよね。
繰り返しを変化させる②【5小節目以降の展開】
では、前項のバリエーション②を使って、その後の展開を考えてみましょう。
|Am F |C G |
|Am F |Dm7 E7 |
6415進行を印象付けたいので、ここからもう一度戻るとしましょう。
|Am F |C G |
|Am F |Dm7 E7 |
|Am F |C G |
ここまでくると、サビを締める展開が欲しくなってきますね。
その場合は、前項バリエーション①をくっ付けて締めるのもアリです。
6415進行の8小節のバリエーションA
|Am F |C G |
|Am F |Dm7 E7 |
|Am F |C G |
|D |Esus4 E |
こうしておくと、例えば楽曲の一番最後のサビ(ラスサビ)でこの8小節を2回繰り返す、という展開も作りやすいです。
メロディのモチーフ(同じメロディのまとまり)が2小節の場合、
最初の4小節でもうすでに結構繰り返した感があるな。。。
という場合は5小節目から締めに向かって展開するのもアリです。
6415進行の8小節のバリエーションB
|Am F |C G |
|Am F |Dm7 E7 |
|F G |F#m7(b5) |
|F G |Asus4 A |
ラストで同主調メジャー( Aメジャー)に解決する、救われて良かったね進行です 笑。
この辺りの展開のバリエーションは、楽曲のサイズ感や時間経過感、またアレンジなどとも関係してくるので「これが正解!」というのはありません。
ただ、自分が曲を作ってて「この感じが気持ちいいんだ」というのがあなたの個性になってくるので、いろんな楽曲を聴いて、いろんなバリエーションを作ってみて
自分的必殺の6415進行の楽曲展開
を持てるようになると結構強みになります。
Lita「悲しみのハンター」での6415進行の楽曲展開
最後に僕のLita時代の楽曲「悲しみのハンター」での6415進行の展開を少し解説しますね。
Lita「悲しみのハンター」
もう19年前ってことで恐ろしく時間経過を感じますが、今また再評価されてもイイんじゃないのとか思ったりもしてます(なんつって笑。ユニバーサルさんサブスク解禁してね)。
楽曲中にあちこち実験的な仕掛けをしていて、よくもまあこんな変態な曲をメジャーで出せたな、と思いますが(Mステでも演奏)中心にあるのは非常にポップな日本的な良質メロディで、もちろんサビは6415進行です。
コード進行解説
キーは A(F#m)なのですが、わかりやすくするためにキーCに移調しますね。
サビはこのような進行になっています。
Lita「悲しみのハンター」サビのコード進行(in C)
|Am F |C G |
|Am F |C G#dim |
|Am F |C G |
|Fm |Fm |
ほぼ前章で解説した通りに、バリエーション展開させています。
4小節目で変化させて、7、8小節目で締めるというシンプルにまとまっている構成です。
で、楽曲の最後、ラスサビではこれでもかといわんほどのリフレインでサビメロを強調し、最後の締めはベースラインが半音で上昇しドラマティックに昇天する、というゴリゴリに押せ押せな展開を作ってます(僕の得意技です 笑)。
映画のように壮大に仕上げたい場合は参考になると思いますので、興味のある方は最後まで聞いてみてください。
まとめ
- 6415進行はサビなどでリフレインで使ってこそ効果のあるコード進行
- 繰り返しが同じだと機械的な洋楽感も出せる。が、飽きちゃうので4小節目のみを少し変化させるバリエーションを作ろう
- どう展開させるかは「メロディモチーフの長さ」が鍵!いろんな楽曲を聴いて時間経過感を身につけよう!