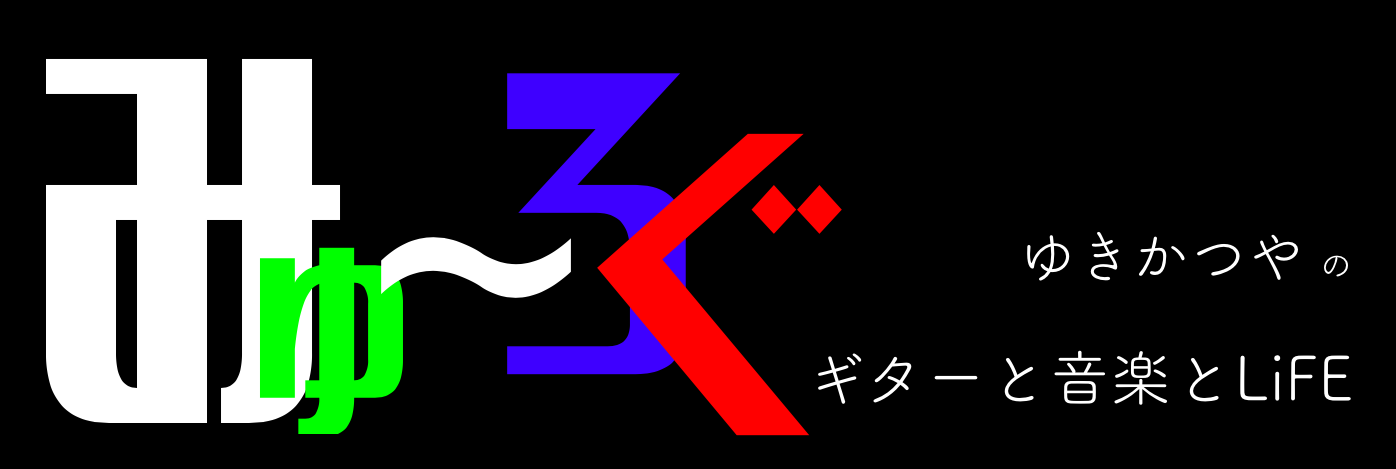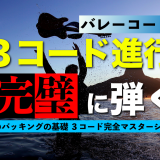あなたは
名曲「翼をください」
を知っていますか?
小学生からご年配の方まで知っている名曲なので、ギターレッスンでも良く取り上げます。
 はじにゃん
はじにゃん
 ゆっきー
ゆっきー
 はじにゃん
はじにゃん
メンヘラ感 笑。
確かに、この「翼をください」しかり
この曲を発表した「赤い鳥」というフォークグループを語るときに
青く、未成熟で、今にも崩れ落ちそうな痛々しい感じ
ある種のメンヘラ(厨二)感
は重要なワードだと思います。
そして、「赤い鳥」のメインメンバーはメンヘラを卒業して
「ハイ・ファイ・セット」へとオトナの階段を登っていくのである。
今回の記事では
・「翼をください」オリジナル楽曲の ” 本当のコード進行”
・その ”本当のコード進行”が持つ意味とバンド解散へ至った理由
を徹底研究・考察します。
今、あなたが弾いている「翼をください」のコード
本当は間違っています。
※この記事は3分ほどで読み終わります
もくじ
「翼をください」サビ8小節目の “本当の” コード進行

まず、結論から書きます。
「翼をください」のコード進行ですが
サビの8小節目は、B♭ではなく B♭M7 である
というのが今回のこの記事のメイントピックです。
ん?何のこっちゃ?
と、思いますよね笑。
「翼をください」を演奏したことがある方は分かると思いますが、コードとかよくわかんない、という方でも
そこから滲み出る人間の感情と音楽的な背景は結構面白いと思いますので、読み物としてお付き合いください。
僕が今回の記事を書くに至ったきっかけ、そして検証、そこから考えられる考察。
順に説明していきます。
楽曲「翼をください」とは?
まず、「翼をください」という楽曲について説明しなければいけませんが
この曲は、現在でも、小学生〜80代まで ほぼ知らない人がいない という名曲なんですね。
なぜかというと、小中学校での合唱の唱歌として取り上げられているからです。
オリジナル楽曲は、フォークグループの赤い鳥が1971年2月5日に「竹田の子守唄」のB面曲として発表した楽曲です。
その後、様々な形で多くのアーティストにカバーされ、合唱曲として現在でも歌い継がれている名曲です。
楽曲のキーは C だが、一点の「血」が混じる(第1の考察)
キーC(ハ長調)の曲というのは、ピアノでいうとほぼ白い鍵盤のみで作られるので、イメージとしては
純白、清らか、神々しい
というイメージになります。
古典クラシックから現代のポップスに至るまで、キーCの楽曲には音楽家たちの純白で無垢な想いが込められていることが多いのです。
「翼をください」は、キーCです。
今わたしの願い事が叶うならば 翼が欲しい
この背中に鳥のように 白い翼 つけてください
この大空に翼を広げ飛んでゆきたいよ
悲しみのない自由な空へ 翼はためかせ ゆきたい
しかし、実はメロディとコード伴奏は白鍵のみで作られてはいません。
Aメロ歌詞の「しろ〜い〜」の「ろ」と「つけ〜て」の「け〜」は F# という黒鍵になっています。
サビの「ゆきたいよ〜」の「よ」と「はためかせ〜」の「せ」はコード伴奏が「B♭」です。
これは僕の考察ですが「血である」と考えます。
白い純白無垢な世界に混じる、一点の血。
それは「悲しみの血」であり、その悲しみから自由になるために空を飛ぶ翼が欲しい
と歌っているのです。
悲しみの血とは、当時の時代背景やフォークという音楽が生まれた精神性を考えると、戦争や抗争、経済的な社会の争い、人間同士の争いを表しているのでしょう。
それを音楽的に表現するために、キーC(ハ長調)で純白な白い理想の世界を、
F#のメロディ音とBbのコード伴奏で、悲しみの血を、
表現しているのです。
この「翼をください」には、そんな
青く未熟な、だが純粋である、理想とする世界を願う祈り、希望
しかし現実は、争いで血が流れる世界であるという苦悩、葛藤
この2つが見事に、歌詞的にも音楽的にも描かれているので
明るい曲調なはずなのに、なぜか悲しく切ない気分にもなります。
そして、その残酷な現実と戦うのではなく、「翼で飛んでいきたい」という青く未熟な逃避の精神は
大人になりきれない永遠の子供性=厨二なメンヘラ感 ※厨二とは「中学2年生」を表す”幼稚である”という意味のネットスラング
を感じさせるのです。
「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」でこの楽曲が使われたのは、そういう
・アダルトチルドレン的な子供達の精神性
・問題を解決するのではなく「飛んで逃げてしまいたい」という青い未熟さ
を表現するためでしょう。
この曲を聴いて、上記したような ”グッと胸が締め付けられる青い未熟さ” を感じるのなら、まだあなたの「子供」は終わってないのかもしれません。
子供性といえば、、、
楳図かずおの漫画「わたしは真吾」では”子供が終わり大人になる”とはどういうことなのか?を圧倒的な表現と世界観で書き切った名作漫画です。
アナタは ”子供が終わる音” を聴きましたか?
サビのコード進行は「カノン進行の変形バージョン」
まだまだ序盤ではありますが、ついついアツくなり楽曲の持つ精神性なんかも語っていますが、結論とも関係する重要な部分なので文字数多めになってます。
さて、今回のメイントピックである「翼をください」のサビのコード進行。
基本的には カノン進行 と呼ばれるコード進行になってます。
キーCのカノン進行は下記のとおり。
|C G |Am Em |F C |Dm G7 ||
しかし、そのままでは何の工夫もないわけで。
この「翼をください」誕生秘話の記事にあるように、作曲・編曲の村井邦彦がゴスペルを意識して書いたために
7つ目のコードは Dmではなく B♭に変えられています。
このB♭というコードが、エバーグリーンな瑞々しい響きを感じさせ、かつ、希望と祈り、苦悩と葛藤を表現したものになっています。
現在一般的に知られている「翼をください」のサビのコード進行は下のとおりです。
「翼をください」サビのコード進行
|C G/B |Am Em |F C |B♭ G |
|C G/B |Am Em/G |F C |B♭ G ||
ほとんど同じ4小節ひと回しを2回繰り返す形ですね。
では、改めて聴いてみてください。
1’11〜1’40がサビの8小節です。
山本潤子さんが歌う、一番高音の主旋律のメインメロディ。
そして、その主旋律に絡む美しいコーラス。
アルトと呼ばれる高い方から2番目のコーラスラインは、2人目の女性メンバー 平山泰代さんが担当しています。
サビ8小節目の “ある違和感”
この曲はギターで初心者でも弾きやすい曲です。
子供でも知っている曲なのでレッスンでもよく取り上げます。
ある日レッスンで、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」のカバーバージョンを聴きながら一緒に弾いてました。
サビのコード進行8小節も先ほどのものと全く同じです。
レッスン終わりで「オリジナル」も聴いてみようかな〜と思い、聴いてみました。
オリジナルはAメロ5小節目でかなり露骨に D/Cにしていたり
なるほど〜微妙に違うもんだな〜とニヤニヤしてましたが、、、、
あれ?サビの最後、、なんか変な音鳴ってんな〜
「翼はためかせ〜」の「せ〜」の前半2拍分
つまり最後の「B♭」の部分ですね。
とても気持ち悪い、、、和音が「クチャ」っと濁っている。
何が原因なんだろう。。。と探ると
あ〜、これ、アルトのコーラスラインの平山泰代さんの歌ってる音だわ。
と、特定。
一番高い主旋律の次の音で、しかも女性コーラスなので結構しっかり目立ちます。
さっきのYoutube動画でいうと 1’34の部分です。
コードネームでいうと B♭M7になる
どうですか?
そう言われれば、確かに気持ち悪い感じがしてくると思います。
これは音楽的に説明すると
ベースが弾いているルート B♭に対して、平山コーラスは A(ラ)の音
を歌ってるんですね。
主旋律が レで、ベースがB♭、これでコードはB♭が確定。
そして、平山コーラスが A音という、ベースに対してメジャーセブンスという音程を歌ってるので
このサビ8小節目の1、2拍目のコードは B♭M7
というコードになります。
僕の思考を書いてみます(主に作曲・編曲的な視点です)
う〜ん、、、これって音楽的にアリなの?
曲の頭から合唱曲的というか、フォーキーな感じで来てるのに、ここで急にこんなモダンなコードつけるかなぁ
もしかしたら平山コーラスがピッチ(音程)が取れてないのか?
いや、待てよ、、、サビ4小節目の1回目のB♭の時はコーラスはどうなってんの?
あ〜、なるほど、、、
ということは、、、
これは、全部の音源確認してみるといいかもなぁ。。。
というのが、この記事を書くに至った全ての始まりです。
コードネームやコードの知識に関しては、下記の記事も参考になると思います。
 【ギター】コードネームの仕組みを知ろう!Part1【音楽理論】
【ギター】コードネームの仕組みを知ろう!Part1【音楽理論】
さて、ここからは「検証」と導き出される「結論」です。
「翼をください」サビ8小節目B♭M7が表現したかったもの

アルバムバージョンで「サビ4小節目のB♭」はどうなっているのか?
さて、まずはこの先ほどから上げているオリジナルの音源。
これは正確にいうと
赤い鳥の4枚目のアルバム「竹田の子守唄」に収録されている、俗にいう「アルバムバージョン」という音源です。
通常「赤い鳥の”翼をください”」といえば、このアルバムバージョンのことを指します。
では、さっき僕の思考で書いた疑問の一つ
サビ4小節目の1回目のB♭の時はどうなっているのか?
平山コーラスが音程を間違って歌っているのではないか?
をまずは検証してみました。
サビ4小節目「飛んでゆきたいよ〜」の「よ〜」の部分ですね。
ここでは平山コーラスは、ベースと同じB♭の音を歌っています。
うんうん、そうなんですよね。
通常考えると、ここのアルトコーラスの音はB♭で正しいのです。
濁りのないスッキリとしたハーモニー。
通常のカノン進行との差別化を計って B♭というコードにしたのだから、それをハッキリと音楽的に表現するためには
B♭のメジャートライアド(B♭、D、F)のみで端的にB♭コード感を出すのが正解です。
平山コーラスの旋律の動きを見てみると、そのサビ4小節目は
コード B♭ → G
平山コーラス B♭→ B
となり、半音で上昇する美しいコーラスラインになります。
これが、ドキドキする高揚感を感じさせ、音楽的にはゴスペル風になり、作曲編曲者の村井邦彦が狙った感じが成功してると言えるでしょう。
平山泰代は間違った音程を歌っているのか?
サビ4小節目は「音楽的な通常のセオリー」により、平山コーラスはB♭を歌っていることは確定しました。
では、サビ8小節目のA音は間違って歌ってしまった、音程が取れなかったのでしょうか?
2番のサビ、3番のリフレインのサビも確認してみたところ。
1番と同じように、4小節目はB♭、8小節目はAを歌っています。
何回も聞いてみると、これはもう疑いようがない。
明らかに8小節目はAを歌うと確信した上で歌っています。
これは何故そう言えるのかというと、ベンド(しゃくり)の始まりの音程が違うからです。
4小節目のB♭を歌うときは、Aから半音ベンドしてB♭に音程を上げています。
8小節目のAを歌う時は、Gから1音ベンドしてAに音程を上げているのです。
平山泰代は決して間違ってなんかいません。
確信して8小節目は A音を歌っているのです。
コードがB♭とB♭M7って、そんなに大きな違いなのか?
つまり、ここまでの検証で言えることは
サビ8小節目は、作曲者と赤い鳥メンバー同意の上で「コード B♭M7」とアレンジして演奏している
ということが言えます。
 はじにゃん
はじにゃん
これは実は大きな違いなのです。
プロで音楽を作っている人間は、普通のメジャーコードなのかメジャーセブンスなのか「ま、どっちでもいいかな〜」なんて適当に決める人はいません。
必ず意図的に確信を持ってメジャーとメジャーセブンスを明確に使い分けます
あの有名なエリックサティのジムノペディ
オリジナルのコード進行は GM7ーDM7の繰り返しですが、これが GーDだったら
あの甘美なとろけるような気怠い微睡み感
は表現できません。
J-POPでは、山下達郎が80年代にメジャーセブンスを使いこなして有名にした一人です。
・都会的な洗練されたシティ・ポップ感
・スッキリとは割り切れない大人の感情、憂鬱さ
メジャーセブンスを多用して見事に表現しました。
ザ・オシャレ感
これに尽きますね。
これらは全て、意図的にメジャーセブンスを使った効果であり、上記のような感情を楽曲に持たせたいというアーティストの意志です。
つまり
(第2の考察)
4小節めのB♭で新鮮さ、勢い、若さ、未熟さ、青さという子供性を
8小節目のB♭M7で、大人にならなければいけない憂鬱、気だるさ、迷い、葛藤
を表現しようとしたのではないか、と思うのです。
なるほど、確かに面白い。
そう考えると、精神性を音楽的に完璧に表現する「よく考えられたアレンジ」だなと思います。
なるほどなるほど〜
う〜ん、、、、、
いやいや、、、、、
ちょっと待った。
この「アルバムバージョン」の音源だけ聴いて、そう判断しても良いものか?
他にもバージョンあるんじゃないか?
あと、この曲って超有名だからめちゃくちゃカバーされてるんだけど、サビ8小節目をB♭M7でカバーしてる人っているのか?
これは検証せねばなるまい。。。
「翼をください」カバー音源でサビ8小節目を検証してみた!

はい、検証しました。
かな〜り!かな〜〜〜り!驚きの結果となりました。
なので、こんなたいそうな記事にしているわけですね。
サビ8小節目をB♭M7でカバーしている人はいるのか?
まずは、カバーの方ですね。
Apple Musicサブスクリプションで「翼をください」で検索すると36曲、カバーが出てきます。
それぞれキーは違いますが、キーCにした場合の「サビ8小節目がB♭M7」にアレンジされているものは
ゼロ
全くありませんでした。
次にYoutubeで「翼をください」と検索すると、まあ沢山あります。
上から約100曲分くらいカバーを聞きましたが
こちらもゼロ。
つまり、、、
この世にある「翼をください」のカバーで、サビ8小節目をB♭M7として再現しているものは1曲も無い
ということが判明してしまいました。
なんてこった。。。
誰もこの事実に気づいていないのか。
それとも、気づいてはいるけど
「そこでB♭M7なんて音楽的に微妙でしょ」と変化させているのか。。。
ちなみに、カバーでの「サビ8小節目の処理」は以下の2パターンに集約されます。
①4小節目と同じで「コードはB♭、ハモリもB♭」
②コードをB♭ではなく、セカンダリドミナントのD7に変えて、D7ーGーCと着地する。
その場合、ハモリの音は「A音」のまま
カバーなので、オリジナルのコードと全く同じにする必要はないのですが、原曲に忠実にカバーする場合は同じコードにしたいところです。
②にいたっては、平山コーラスのA音こそ変えてはいないものの、コードをD7と変化させているので、これはもう別の曲と言ってもいいリハーモナイズです。
真に「翼をください」を愛しているのなら…
これはもう、音楽家の信念というか、執着心というか、、、
僕がそうである、ということなのですが
その楽曲を本当に愛していて、オリジナルの作曲者、編曲者へのリスペクトがあるのなら
完コピで再現すべきである ※出来る限り最大限の努力をするという意味で
と思っています。
主旋律であるメロディ、それにどういうハーモニーのラインをつけているのか
コードは何になるのか、和声的にはどうなっているのか、リズムはどうなのか
特に、先ほど書いたように、普通のメジャーなのかメジャーセブンスなのか
これは楽曲の根幹の雰囲気を決定するほどの大きな違いであり、そこには必ず作編曲者の意思、意図があるのです。
あえてメジャーセブンスにしている理由があるのです。
僕自身が作編曲をする人間なので、作る側の気持ちは痛いほど分かります。
結論:「翼をください」サビの真実のコード進行
ということで。
この記事をここまで熱心に読んで頂いた、赤い鳥の「翼をください」がたまらなく好きなアナタ。
今後、ギターやピアノでコード伴奏する場合は、サビは以下のように演奏しましょう。
「翼をください」サビの真実のコード進行
|C G/B |Am Em |F C |B♭ G |
|C G/B |Am Em/G |F C |B♭M7 G ||
もちろん「ハーモニー全体としてB♭M7になっていれば良い」ので
コード伴奏は「B♭」だとしても、平山コーラスを担当するハモリの人が「A音」を歌えばOKです。
まあでも、それだとハモリの音が浮いて聞こえるかもしれないので、コード楽器も「B♭M7」を弾くのが一番良いですね。
いや〜、解明できて良かった。
ちょっと音楽が分かる人に「あれ?そのサビ8小節目、なんかハーモニーおかしくない?間違ってない?」と言われても
いや、オリジナルの「翼をください」はココはB♭M7なんですよ
アナタの方こそ、よく分かってないんじゃないですか?(上から目線で)
と言い放ちましょう。
じゃあ、これでこの記事も終わ、、、、、
あ、そうかそうか。
まだ、「赤い鳥」本人たちのその他の音源での確認してないです、、、ね?
いやいや、もうそんなことする必要ないでしょ。
本人たちは、明確な意思を持って全ての音源でB♭M7を演奏しているはずですよ。
分かりきったことでしょ。
まあでも、ライブバージョンなども含めると、いくつかバージョンがあるみたいですし
一応調べておきましょうか。。。無駄足だとは思いますが。。。
「赤い鳥」本人による「翼をください」全音源を聴き比べて検証した!
前フリが長くてすいません。
これだけのフリがあって、このまま終わるわけはありませんね。
そうです。
本当の物語はここから始まるのです。
驚愕の事実が判明し、そして、そこからさらに深まる謎
人間関係や感情のぶつかりまで内包し、ついにはグループ解散までに至る道のり
見ていきましょう。
時系列順に「翼をください」のいろんなバージョンの「サビ8小節目」を検証!
まずは、間違いのない事実を書きます。
いろんなバージョン違いで、あの8小節目は全部B♭M7で演奏されているのか
これの検証結果を書きます。
分かりやすいように、判明している範囲で時系列順に書いていきます。
検証音源は
・Apple Musicサブスクリプションで聞ける「赤い鳥」の「翼をください」収録作品
・Youtube、ニコ動で確認できるライブ、その他の「赤い鳥」本人による「翼をください」の音源
です。
①「翼をください」シングルバージョン
1971年2月5日発売
シングル「竹田の子守唄」のB面として世に発表された、一番最初のバージョンです。
ソフトロック調の軽めのシャッフルでアレンジされている唯一のバージョンで、当時JALのCMに起用されていました。
サビ8小節目は「コード B♭M7」「平山コーラスはA音」です
②4thアルバム「竹田の子守唄」収録の「翼をください」(アルバムバージョン)
1971年7月25日発売
最初から何度も出てきている一番お馴染みのアルバムバージョンです。
サビ8小節目は「コード B♭M7」「平山コーラスはA音」
③ライブ 1971 / スタジオ・ライブ 収録の「翼をください」
1971年12月20日
初期のスタジオ収録ライブ音源。
ライブでこれだけの圧倒的な歌と演奏を聴かせる実力は本当に素晴らしいです。こんな高揚感のあるライブ今は観れないなぁ。
サビ8小節目は「コード B♭M7」「平山コーラスはA音」
④ライブバージョン1・ポン太&大村憲司炸裂バージョン
1972年6月以降
いわゆる中期のライブバージョン。村上”ポン太”秀一と大村憲司が炸裂してて好きです。若さっていいね。
サビ8小節目は「コード B♭M7」「平山コーラスはA音」
⑤「翼を下さい」英語バージョン
1972年11月20日発売
もともとアルファレコード社長の村井邦彦の仕掛けで「和製カーペンターズ」的な、洋楽ソフトロックなコーラスグループの要素も持っていた赤い鳥が海外向けに出した英語バージョン。
英語バージョンの時は「翼を下さい」と表記されます。
アレンジが大幅に違い、コーラスアレンジも変更(平山コーラスはほぼ聞こえない)されてるため検証外ではありますが一応。
サビ8小節目はコード「B♭」
⑥ライブバージョン2
1973年5月1日(ソースはYotubeだが詳細不明)
ドラムが渡辺俊幸に代わったいわゆる後期のライブバージョン。今回の検証音源の中では一番テンポが遅く、重たいビートです。
サビ8小節目は「コード B♭M7」「平山コーラスはA音」
⑦ライブバージョン3
1973年4月以降(詳細不明)
渡辺俊幸加入後の後期のライブですが、詳細は不明です。テレビか公開収録のものみたいですね。
アレンジの方向はライブバージョン2とほぼ同じです。
しかし、なんと、このライブ音源では、あのサビ8小節目を
平山コーラスはB♭を歌っているのです!
何度聞いても、前述した「ベンドの開始音」から検証しても、どう聞いても
B♭を歌うと確信してB♭を歌っています。
つまり、4小節目の1回目のB♭と全く同じように、8小節目も同じB♭を歌っているのです。
サビ8小節目は「コードB♭」「平山コーラスはB♭」
な、なんてこった。。。どういうことなんだ
今までは確信を持って、おしゃれなA音を歌ってきたじゃないか
それで、最後はハーモニーをB♭M7にすることで、音楽的にはカーペンターズ的な洋楽ソフトロック・ゴスペル調を提示し
さらに歌詞の精神面ともリンクさせ、未熟な若さからオトナへと移りゆく不安定な感情を表現したんじゃなかったのか?
いや。。。何かの間違いかもしれません。
しかし、次の音源で疑惑は確信へと変わり、新たな考察を生むのです。
⑦ミリオン・ピープル〜赤い鳥コンサート実況録音版
1973年12月25日
この次の年1974年7月にラストアルバムを発表し「赤い鳥」は解散します。
なので、実質公式な音源として残っている解散前の最後のライブ音源での「翼をください」がこのバージョンです。
そして、また驚愕の事実が発覚します。
このライブバージョンでも
サビ8小節目は「コードB♭」「平山コーラスはB♭」
を歌っているのです。
ラストに何度も何度もサビのリフレインがありますが、全てB♭を歌っています。
これが事実です。
番外編① 謎のアコースティックライブバージョン
時期不明
今回の検証には当てはまらないのですが、サビ8小節目をどう演奏しているのか、バンド的な歴史が垣間見える資料として紹介します。
キーがなぜか半音低いBになってますが、これは多分テープからデジタル化した際のピッチのズレだと思われます(本来はキーCでしょう)。
問題のサビ8小節目は「コードはD7」「平山コーラスはA音」
になっています。
おっと、これはまた新しいパターンですね。
アコースティックバージョンなので、アレンジを変えたのでしょうか。謎です。
番外編② 後年の山本潤子のソロによる「翼をください」
これはかなり最近のTV番組での山本潤子さんのソロによる「翼をください」ですね。
見てもらえればわかりますが、サビ8小節目は D7で演奏されています(アコギやバックも)。
奇をてらわず、特にひっかりもなくスッと聴かせるにはD7が有効なんですね。
プロのカバーでもD7で演奏している方もいました。
事実のまとめ:1973年のどこかで平山コーラス「A音からB♭へ」の変化が起こっている
さっくり表にまとめた方が分かりやすいので、まとめてみましょう。
| ★バージョン | ★発表年月日 | ★サビ8小節目のコード | ★平山コーラスの音 |
| ①シングルバージョン | 1971年2月5日 | B♭M7 | A音 |
| ②アルバムバージョン | 1971年7月25日 | B♭M7 | A音 |
| ③ライブ1971 | 1971年12月20日 | B♭M7 | A音 |
| ④ライブバージョン1 | 1972年6月以降 | B♭M7 | A音 |
| ⑤ライブバージョン2 | 1973年5月1日 | B♭M7 | A音 |
| ⑥ライブバージョン3 | 1973年4月以降 | B♭ | B♭ |
| ⑦ミリオン・ピープル | 1973年12月25日 | B♭ | B♭ |
主要な検証音源を並べてみました。一目瞭然ですね。
ここから言えることは、、、
1973年のどこかのタイミングで
ライブで「翼をください」を演奏するときに、平山泰代さんはサビの8小節目のコーラスをA音を歌わずに、全てB♭を歌うように変えてしまった
これが、今回の検証結果での事実の全てです。
さて、ここまで読んで頂いた方、どう思われますか?
なぜ、平山泰代さんは音を変えて歌うようになってしまったのでしょうか?
それも、グループ解散直前に。
いや。。。
もしかしたら。。。
これこそが、「赤い鳥」解散の兆しではないでしょうか?
グループ内で何かの歯車がズレていった兆候が、このコーラス音の些細な変化に現れているのではないでしょうか?
「翼をください」誕生〜赤い鳥 解散に至るまでの物語【妄想考察】
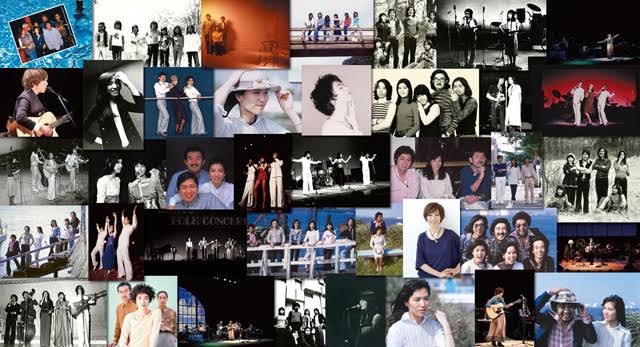
さて、ここまで長々と書いてきた「翼をください」のサビ8小節目のコードの秘密。
そして、それがなぜか変化をしてしまったという「事実」
音楽というものは、精神、魂の表れた形である
と僕は信じています。
なので、些細な変化、微妙な違いというのは、その精神に変化が現れたから変わったのだ、と考えます。
これがジャズなどのアドリブであれば、毎回演奏内容は変わるので、その精神を探るのはなかなか難しいですが、今回題材にしているのは「完全にアレンジされたポップス」です。
これはクラシックと同じで「再現芸術である」と言えます。毎回同じように再現演奏してこそ価値があるのです。
前述しているように「サビの8小節目のコーラスをB♭M7」にしたのには、必ず明確な理由があるはずです。
では、この「後期 赤い鳥」において「翼をくださいのサビ8小節目を平山コーラスはB♭にする」と変化させたことにも、当然意味と明確な精神性があると考えます。
では、その意味とは一体なんなのか?
「翼をください」が誕生したところから想いを馳せ、考察してみましょう。
初期〜「翼をください」作曲&アレンジ期
村井邦彦(以下 村井)「よし、出来たぞ!サビのコード進行はカノン進行で決まりだな。この曲は実はゴスペルのイメージがあるんだよ。皆で手拍子をしながら合唱しまくるあの感じだよ。
で、普通のカノン進行ではなくて、4小節目の頭のコードをB♭にしたいんだよ。どうだい?いい感じだろ?」
メンバー「凄くいいよ!そうしよう!じゃあ、サビのコーラスだね。主旋律が新居がめっちゃ高いメロディになってるから、ハモは下の音程にいくしかないね。主旋律と3度でハモるようにアルトコーラスにしよう。これもキー高いから女性の平山ちゃんお願いね。」
平山「となると、、、このB♭のとこはどうなるのかしら?主メロが ”飛んでゆきたいよ”の “い〜よ〜” で ”ド〜レ〜”でしょ。ハモは「ソ〜ファ〜」って下がるのが和声的には美しいんだけど、、、」
メンバー「えーとね。確かにそうなんだけど。。。それだと”飛んでいく感じ”が出ないなぁ。主メロと同じくハモも上に上がろうよ。コードがB♭だから “ソ〜♭シ〜” だね」
平山「ソ〜♭シ〜か。ハモリのラインが音が跳躍しちゃって、あまり美しいとは言えないよね」
メンバー「コーラスの和音としては素直にB♭になるから良いんだけどね。若くて勢いのある感じ、高揚感を感じるじゃん!」
村井「コーラスラインとしては、音が上がる方向なら “ソ〜ラ〜”と順次進行する手もあるぞ。4度音程が繋がってフィフスディメンションっぽくて良いじゃないか!」
メンバー「ほんとだ!モーダルでお洒落な感じだね!僕らの目指すカーペンターズみたいな洋楽的なハーモニーだ。B♭に対して平山ちゃんがAを歌うんだから、コードネームはB♭M7になるんだね。めっちゃお洒落じゃない!」
平山「ちょっと難しいね。音程取りずらいけど練習すればなんとかなるかな。4小節目と8小節目と2回ともAを歌うの?」
メンバー「いや、1回目は提示だから素直にB♭、ラストは変化をつけてB♭M7」
村井「なるほど。飛んで逃げることが本当に正解なのか、その不安と焦燥を表現するラストのメジャーセブンスか。歌詞と楽曲のコンセプトにもがっちり合ってる。それでいこう!みんないいな!」
メンバー全員「はいっ!」
中期〜「翼をください」発表後&ライブ
メンバー「いや〜、この曲が世間に受け入れてもらえて良かった。売り上げも好調みたいだし、僕らもどんどん活動していけるね。」
〜まさに「理想とする音楽」を世に出せたことを喜ぶメンバー達〜
平山「でも。。。ちょっと気になる事があるのよね。。。」
メンバー「どうしたんだ?」
平山「時々ね、音楽に詳しい評論家から言われるのよ。
”君の歌っているサビのコーラスラインの最後のとこは音程が間違っていないかね?1回目はBbを歌ってるのに、2回目はちょっと低くてAに聞こえるよ。アレは音程を間違ってるんじゃないのか?”
ってね。。。」
メンバー「確かに。この曲を学校の合唱曲にしたいっていう話もあるんだけど、その問題の部分は小学生には難しくて歌えないから変えられないか?って僕も言われたよ」
他のメンバー「おいおい、何を言ってるんだ!アレは俺たちの音楽的なこだわり、哲学なんだよ!2回目はBbM7だからこそイイんじゃないか!
そこにこそ、俺たちが表現したかった、大人と子供、未熟と成熟、黒と白、希望と不安。。。色々な意味を持たせたんじゃなかったのか?」
平山「もちろん分かってるわ。でも。。。私、間違ってるって言われるの嫌だわ。。。」
メンバー「うーん。。。。」
B♭M7を押し通すのか、捨てるのか。
売れる為、広く聞いてもらうために分かりやすさを取るのか。
こだわりを持ち続けるのか。
そこがまさにアーティストとして問われるところ。
村井「よし。。。じゃあ、こうするのはどうかな?
サビ1回目は平山コーラスはB♭、これは異議なしだろ?
2回目はコーラスの音をAのままにしたいなら、コードをD7に変えてしまおう。」
そして、あの謎のアコースティックライブバージョンが生まれる事になる→D7バージョンの誕生
さらに村井の案で、唱歌として学校などで歌う場合は「サビ8小節目もB♭にする簡易バージョン」で提供することにした
→現在も皆がカバーする「どっちもB♭バージョン」の誕生
その代わり、赤い鳥のライブでは「これが本当のサビ8小節目のハーモニーだ」としっかり表現するために、本来のB♭M7を歌おうじゃないか!と平山はA音を歌い続けた。
後期〜歯車の狂い始め〜解散
バンドは「翼をください」のヒットと共に、知名度を増していった。
村上秀一、大村憲司が参加した中期は、バンドとしてもセールス的にも最高の盛り上がりを見せたが、徐々にその熱も冷め、1973年4月に村上は脱退。ドラムは渡辺に変わった。
〜あるライブ前、平山と後藤の会話〜
後藤「平山ちゃん、お疲れ!ん?。。。どうしたんだ?暗い顔して」
平山「こないだの公開収録ライブのあとさ、、、また言われちゃったんだよね。
”翼をくださいのラスト、コーラスの音が気持ち悪い”って」
後藤「またか。。。ずっと言われてるよね。俺は。。。実は。。。あのB♭M7のハーモニーさ。
なんか、ずっと違和感があるんだよ。もちろん、その違和感をあえて出そうって事で皆で話したんだけどさ。
そうじゃなくって。。。。
俺はあんなカーペンターズとかフィフスディメンションとかの洋楽的なアプローチは、最近あまり好きじゃなくてさ。
表面的なハーモニーのテクニックとかお洒落な感じじゃなくてさ。
もっと内面的な、精神性を表現したいっていうか。もっと純粋なピュアな。。。まあ、幼稚な子供的な考えって言われるかもしれないけどね。心を表現するために、深い歌詞とか、シンプルな音楽表現とか。
うまく言えないんだけどさ。。そんなことを思ってんだよね」
平山「ビックリした。。。。そうだったんだ。。。。
実は私も似たようなこと、思ってんだよね。複雑なハーモニーとかではなくて、シンプルに心を伝えたい。
いってみれば、もっとフォーク的な部分を大切にしたいのよね」
後藤「そうか、、、じゃあさ、、、今度のライブで、あの部分、B♭を歌ってみれば?
ずっと、A音をこれまで歌ってきたわけだし、今更メンバーはそこには気づかないよ。平山ちゃんの主張も俺の主張も通す事ができるかもよ。小さい事だけどね。」
平山「そうね、、、、そうしてみるわ。あ、その後にはライブレコーディング(ミリオンピープル)の話もあるじゃない。それもB♭で?」
後藤「そうだね。音源には残っちゃうけど、そこはもう、そうなれば話し合うしかないよね」
平山「分かったわ。
私、2回ともB♭を歌うわ!」
そして、その後「翼をください」では、平山は2回ともB♭を歌い始めた。
平山がそうする事で、2回目のハーモニーはB♭M7ではなくB♭になった。
平山と後藤は、こっそり目を合わせ、そのシンプルなハーモニーに笑みを浮かべた。
しかし、ライブ実況録音「ミリオン・ピープル」の発売後に恐れていた事態が起こってしまった。
いや、正確にいうと
いづれ起こるべき事態がついにやってきた、というところだろうか。
〜あるリハーサル終りの夜〜
山本「みんな、ちょっと聞いてくれ。
先日のライブレコーディングをミックスで聞き直していたんだが、ちょっと気になる事があるんだ。
平山、、、お前 ” 翼をください ” のラスト、B♭でコーラス歌ってるよな。どういう事なんだ?」
〜しばしの沈黙の後、意を決したように平山が口を開いた〜
平山「私は、もうずいぶん前から、あそこはB♭を歌ってるわ。B♭M7の微妙なハーモニーを歌うのが、、、、嫌になったの。
独断で勝手に変えてしまって、、、ごめんなさい」
山本「そうだったのか、、、いや、今まで気づかなかった俺も悪いが、、、
なぜB♭M7が嫌になったんだ?あれはこの”赤い鳥”というグループの精神的な象徴なはずだろ?」
〜黙る平山、そして、一人の男が口を開く〜
後藤「俺と平山で話をして、B♭を歌えと、俺も賛成したんだよ」
〜後藤は、ゆっくりと、丁寧に
あの日 平山と話して精神的なつながりを得た事、を山本に全て伝えた
山本は黙って聞いていた
そして、重い口を開いた〜
山本「そうか。。。君たちがそこまでの想いで繋がり、あの8小節目をB♭で歌っていたことは理解できた。
つまり、適当な気持ちではなく、明確な意思と想い、主張がありB♭に変えて歌ったということだよな。
俺たちが、最初にB♭M7にしたのも、同じく明確な意思と主張があってのことだ」
後藤「その通りだな、つまり、、、」
山本「つまり、俺たちは明確な意思と主張のもとに、完全に異なる方向性を向いてしまってる、という事になる」
後藤「そうなると、もう一緒にグループを続けていくのは難しい。そうだよな?」
山本「そうだな。。。」
〜いつの間にか、窓からは柔らかい朝日が差し込んでいた〜
山本「”ミリオン・ピープル”はこのまま発売する。それが俺たちの意思だ。
そして、今後 ”翼をください”は、ライブでは演奏しない。いいな?」
後藤「分かった。。。
あと一枚、アルバムの契約が残ってるが、それはどうする?」
山本「それは、もちろん作る。契約だからな。そして、それが俺たちのラストアルバムだ。。。」
1974年7月5日 「書簡集〜ラスト・アルバム」発売
そして、1974年9月
赤い鳥、解散。
そして、伝説へ…
その後、山本夫妻(山本とリードボーカル新居は結婚)と大川は、ハイ・ファイ・セットを結成。
元々の音楽性であった、カーペンターズ的な洋楽志向の洗練されたハーモニーを追求。荒井由美から楽曲提供も受け、ニューミュージックの幕開けを代表するグループになった。
後藤と平山は結婚し、紙ふうせんを結成。
内面性を一番に考え、シンプルな曲調でフォークのあり方を追求した。
赤い鳥は「翼をはためかせ」て子供を卒業して「ハイ・ファイ・セット」という大人の階段を登っていった
そして、そこに残り、より深いフォークの精神性、メンヘラ的な人間性を追求する決意をしたのが「紙ふうせん」だったのではないだろうか
しかし、実は、一見音楽的な方向性で袂を分けたように見えるが
その根底に流れる精神性は実は同じものである
と気づくには、まだ彼らは若すぎたのかもしれない。
そして、いつの日か、また再び
「翼をください」のサビ8小節目で
完全に成熟した形でB♭M7のハーモニーが聴けること
を信じて、今回の全ての検証と考察を終わりにしたい。
終わりに
最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。
これから「翼をください」を聴くとき
たった1つのサビのコードに、もしかしたらそんな物語があったかもしれない
と、思い出してもらえると嬉しいです。
そして、記事中にも書きましたが、そんなたった1つのコードに
音楽家は魂と信念を込めて作っているものだということを実感してもらえたのではないでしょうか。
これから「翼をください」を演奏するとき、僕はその精神にリスペクトしつつ
サビの8小節目の1、2拍目をB♭M7で演奏します。
では。
※文中の会話は全てフィクションです